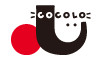チュニジアに来て、三日が過ぎた。
ようやく宿の周りの空気感が、
肌に馴染み始めてきたような気がする。
この数日、日中の陽光は驚くほどに強く
街には半袖で歩く人の姿も目立つ。
けれど、日が傾き始めると空気は一変し
刺すような冷気が街を包み込む。
行き交う人たちは厚手のコートを羽織り
足早に家路を急ぐ。

僕の宿は古い西洋建築で
天井は高く風情があるが
暖房がない。
冷え切った部屋で布団に入りながら
撮影した画像を整理し
ブログも書いている。
救いはベランダに干した洗濯物が
夕方にはパリリと乾いていることだ。
着替えの少ない自分にとって、
干していた洗濯物が乾いた肌ざわりになっていることが
何よりの贅沢に感じられる。

そして、ラマダンが始まった。
祈りと断食の月。
はじめて体験するラマダンが
この街にどのような影を落としていくのだろうか。
僕はいわゆる「観光」というものが苦手だ。
決められた景色を、決められた角度から眺めることに、
どこか心許なさを感じてしまう。
けれど、宿の主人が「安く連れて行ってあげるよ」と
微笑むので、その好意に甘えてみることにした。
車で三十分ほど走ると、カルタゴの遺跡が現れた。

フェニキア人が築き、
その後、ローマ帝国の侵略によって
徹底的に破壊された街。
ローマはその残骸の上に
自らの都市を執拗なまでに重ね書きしていった。
歴史の層をなぞるように歩いてみるが
あまりに整備されすぎたその場所は
どこか切り取られた標本のようになっている。
生命の気配を感じように感じるものがない。
連綿と続いてきたはずの時間の大河が、
ある場所でぷつりとカットされ、
公園という形に押し込められているようで、
戸惑いを覚えた。
保存というのは、時間を止めてしまうことだ。
そこには、紡がれてきた気配も失われてしまう。
その寂しさを感じてしまった。

次に訪れたシディ・ブ・サイドは、
眩しいほどに白く、そして青かった。
観光の街であることを隠そうともしないエリアだが、
それを差し引いても、僕の視線を引きつけて
離さない美しさがあった。

壁は白、扉と窓は青。
徹底されたその色彩のルールは、
一九一〇年代にこの地を愛したフランス人画家、
ルドルフ・デルランジュ男爵の提案から
始まったのだという。

気候や環境という人間には到底制御できないものに対し、
色という象徴的な手段で順応し、
街を守ろうとした一人の男の意志と住民の思い。
空の青、海の青、そして扉の青。
その幾重にも重なる青のグラデーションを
眺めているうちに
自分の生まれ育った街の色に思いを馳せる。
僕の育った街は、一体何色なのだろう。
街を考えるということは、
その街の色を考えることでもある。
地中海の強い風に吹かれながら、
町には色があることに
気づかされたような気がした。