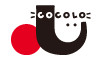折りたたみ自転車と列車でスリランカを巡った45日
<シーギリヤロック&ピドゥンガラロック>
スリランカで最も観光客に人気があるといわれるシーギリヤロック。このあたり一帯は山の少ないフラットなジャングルが広がる。そこにシーギリヤロックがぽこっと突き出ている。なぜこのような形ができあがったのかはわからないが、神様の仕業!だとすると納得してしまうほど、見れば見るほど不思議な岩山だ。
観光地にはあまり興味がないが、ここには行ってみたいと思っていた。旅に出る前に、シーギリヤロックについて、ネットで下調べをしていると、シーギリヤロックの向かいにあるピドゥンガラロックからの景色の方が絶景だという記事を見つけた。ピドゥンガラロックは、欧米人は多いが日本人はまだ少ないとも書いてある。その記事をネットで読んで、2つの岩山に登ろうと決めていた。
シーギリヤロックに行くなら、シーギリヤの町に泊まればいいものを、なぜか自転車で1時間ほど離れたハバラナという町に宿をとってしまった。しかし、ここが思いのほかよくて、この宿をベースに2つの岩山をめぐることにした。宿のオーナーに「明日の早朝、自転車でピドゥンガラロックに向かうから、いなくても心配しないで」そう伝えると、オーナーが「ダメだ!絶対にダメ」という。「何がダメ?静かに出ていくから」。そういうと「何時に出るんだ」と聞く。「ピドゥンガラロックの頂上で日の出を見たいから4時に出るつもりだ」。「ダメだ!絶対にダメだ!日の出前だと道路に象がいるかもしれない。彼らに遭遇するととても危険なんだ。鼻で飛ばされて踏み潰されしまうぞ!」そう言ってきた。びっくりだ。スリランカの国立公園に野生のゾウがたくさんいることは知っていたが、道路に出てくるとは知らなかった。「おれのトゥクトゥクで送るから」と商売っ気のあるオーナーがいう。「ただで送ってくれるの?」笑いながらそう聞くと値段をふっかけてきた。やっぱりか。野生の象が危険なことをいいことに、儲けようという魂胆か。その脅しには乗らない。話にならないという表情で「いらない!自転車で行くよ」。「どうなっても知らないからな」。そんなやりとりのあと部屋に戻った。さっそくネットで「スリランカ 象 事故」で検索すると、野生のゾウは危険だという記事が出てくる。フランスのAFP NEWSの記事のなかには、毎年50人程度がゾウに命を奪われていると書かれている。オーナーが言ったことは本当だったんだ。すぐさま、1階に降りて、オーナーとトゥクトゥクの料金交渉。明るくなれば大丈夫というから、自転車を一緒に積み込んで片道だけお願いすることにした。

朝4:30にゲストハウスを出発。幹線道路から外れると、ジャングルのなかを通る一本道に入った。舗装はされているが、なんだか不気味だ。運転するオーナーの背中からも少し緊張が伝わってくる。道端にゾウのウンチが落ちているのを何度も目撃した。やっぱりトゥクトゥクに乗せてもらって正解だったようだ。
20分ほど走ると、登山口のある寺院前に着いた。ここでオーナーと別れた。境内に入ると受付がある。シーギリヤロックのゲートは8時オープンだが、ここのお寺は早朝から開いている。入山料500ルピー(約300円)を払い、ヘッドライトを頼りに山道を早足で登る。寺の境内から20分ほどかかっただろうか、最後に大きな岩の隙間をよじ登っていくと頂上に出た。あたりはまだ暗かったが、すでに30人以上の人がいた。多くが欧米人のカップルやグループだ。はしゃいでいる人たちもいるが、多くは静かに夜空を見上げている。目の前にシーギリヤロックのシルエットがうっすらと、遠くにはポツポツと町の光が見えていた。

東の夜空が青みをおびはじめ、少しずつ夜が終わっていく。世界が入れ替わる時間だ。これまで何度も何度も夜明けを見てきたが、飽きることがない。地上に広がる風景は違っても、空は同じなのだ。世界中が繋がっている。
シーギリヤロックの背後から朝日が昇ってくることを期待していたが、白み始めた空は全く違う方角だった。インスタ用なのか自撮りに忙しい人たちもいたが、多少の緊張感を持って太陽を迎えようとしている人たちもいる。清々しい光景だ。結局、雲が多くてすっきりと太陽を拝むことはできなかったけれど、特別な時間をこの場所で過ごせたことがうれしくもあり不思議な気分でもあった。


夜明け前から登っていた人たちは、日が昇ると早々に下山を始めた。8時から入山できるシーギリヤロックに向かうのだろうか。もしくは次の町へと移動していくのか。会話を交わした人は一人もいなかったが、そっと写真におさめた人は何人かいた。帰国後、日本の大阪という場所でぼくが彼、彼女をパソコンの画面で見ている。連絡先もどこの国の人かもわからない。だけど、パソコンのなかにはシーギリヤロックとともに彼らがいる。ぼくも誰かの写真のなかで、そういう存在になっているのだろうか。それはどこの国の人だろうか?そんな想像が膨らむことも、写真の面白さのひとつかもしれない。
8時のゲートオープンにあわせてシーギリヤロックの麓にやってきた。受付で25ドル(高いなぁ)を払ってチケットを購入。昼間に来ると登るのに渋滞するそうだが、この時間だと人はそこそこいるものの、階段で立ち往生するようなことはない。目の前にそびえ立つ岩山へと近づいていく。絶壁に作られた階段を上ることおよそ30分で頂上に到着。頂上はテーブルの上のように開けていて、そこにかつてあった王宮の遺構が広がる。よくもこんな場所にこれほどの資材を運び上げ、組み上げたもんだと驚くばかりだ。





かつてこの岩山は仏教僧たちの修験場だったそうだ。しかし、今から逆のぼること約1600年前、この岩山を仏教僧から奪い取り、その頂上に王宮を立てた王様がいた。狂気の王と呼ばれるカーシャパがその人。父親が王位についていたとき、異母兄弟の弟に王位継承権を奪われるのではないかと、父親を殺して自分が王になってしまった。さらには、弟に攻め込んで来られるのを恐れて、断崖絶壁の岩山の頂上に王宮を建ててしまったというわけだ。労働者として働かされた人たちはたまったものではなかっただろう。弟は一旦インドに逃れたものの、戻って来て攻め込むと、カーシャパ王は自害して果てた。そんな古の物語を想像しながら眺めてみると、また違った見方を楽しめるかもしれない。




シーギリヤロックを下山して昼ごろ一旦宿に戻った。日中の暑い時間を使ってカメラのデータをパソコンに落とす。ゆっくりとくつろぎながら体を休めたあと、再びピドゥンガラロックを目指す。今度は夕日を見るためだ。朝の余韻が忘れられず、もう一度あの空間に身を置いてみたかった。「暗くならないうちに帰ってきてね!」ゲストハウスの奥さんにそういって見送ってもらう。未明に通った道路は昼間に通ると、なんてことはない普通の道路だ。ゾウのウンチは落ちているが、怖くもなんともない。自分が緊張していただけだったと思いなおした。





ピドゥンガラロックの頂上に着くと、シーギリヤロックが見える方角に人が多くいた。それ以外のところはまばらだ。ピドゥンガラロックの頂上は傾斜が多いが、シーギリヤロックよりも広い。人工物が何もない空間が空に向かって広がる。気持ちがいい。ただ、太陽に熱せられた地表の空気が上昇気流となって昇っていくのか、吹き上げてくる風がすさまじい。ゆるくかぶった帽子だと簡単に持っていかれてしまう。台風並みの突風に耐えながらも、西の地平に傾いていく夕日を、多くの人が眺めている。朝日をこの場所で迎え、夕日を同じ場所で見送る。なんと贅沢な日なんだろう。
ぼくは空を見るのが好きだ。山や川は形状が変化してしまうけれど、空は、戦国時代も、縄文時代も、きっとそう変わらない。もしかすると、恐竜の時代もこんな空だったかもしれない。太古から続く空を今の自分が見ている。そのことがうれしい。目には見えない何かで繋がっている。
夕日が沈んだ後も、満足感に浸りながら薄暮の風景を写真を撮っていたが、気がつくとまわりには誰一人としていなくなっていた。やばいかも。機材をしまってリュックを背中に背負った時、すでに暗くなっていた。脳裏をかすめるものがある。ゲストハウスの奥さんの「暗くならないうちに帰ってきてね!」という忠告だ。夜になるとゾウが出る。危険だ。転がるように急いで下山し、自転車にまたがった。周りに人はほとんどいない。暗い夜道を猛スピードで走り抜けるしかない。覚悟を決めてペダルを漕ぐ。車もバイクも全く通らない。そのなかを息を切らしながらもスピードを緩めず必死に走る。途中、前からバイクが3台やってきた。彼らがすれ違いざまに「◯◯◯◯エレファント◯◯!」と言った気がしたが、もう止まりたくない。一刻も早くここを抜けたい。しかし、さきほどの彼らが言った言葉が気になっていた。エレファント?どうしよう、この先にいたら。そのとき、後ろから車のライトが近づいてきた。その車はスピードを落とし、しばらく後ろを走ってくれている。先を照らしてくれているのだろうか、ありがたい。車のエンジン音がここに人間がいることを知らせてくれているのかもしれない。そう思うと少し安心だった。しばらくすると、後ろにいた車がスピードをあげて追い抜いてきた。「ありがとう!」そう大きな声で手を振ると、また、スピードを落として前についてくれるではないか。スピードは30キロちょっと出ているが、これはついていくしかない。ぼくをゾウから守ってくれているんだ。その優しさに熱いものがこみあげてくる。それから10分ほど走っただろうか、民家や街灯が出てきたあたりでクラクションが「ピッピー!」と鳴り、その車はスピードをあげて走り去っていった。ぼくは車のテールライトが見えなくなるまで「ありがとう!」と日本語で力いっぱいに叫び続けながら走った。ありがとう!と心の底から本気で叫んだのはいつぶりだろうか。しばらくすると大きな通りに出た。助かった。安堵と感謝の気持ちで放心状態になりながら、ゆっくりと自転車を漕いでいると、先ほどの車が道から少しそれた車庫前に止まっているのが見えた。ドライバーが車の前にいる。彼に向かって「本当にありがとう!」と叫ぶと、大きく手を振り笑顔で「良い旅を!」と言ってくれた。
旅を終えた時、心に深く残るのは、きれいな景色より、人の厚意であり言葉だ。もう一生彼に会うことはないだろうが、彼から受けた厚意をぼくは誰かに渡したい。国境を超えて厚意が巡っていく。それが旅の醍醐味でもあるのだ。